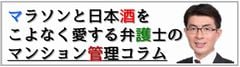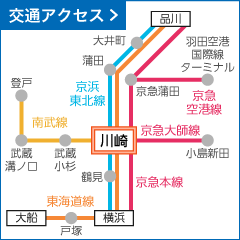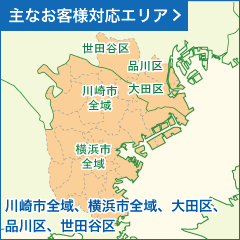被相続人が相続人の債務を肩代わり。果たして遺産分割での特別受益となるか?
「生計の資本としての贈与」
被相続人による相続人に対する贈与が民法上の特別受益にあたるといえるためには、当該贈与が「生計の資本としての贈与」(民法903条1項)に当たる必要があります。
ところで、被相続人が生前相続人の債務を肩代わりするということは比較的よく見られることですが、こうした債務の肩代わりは特別受益における「生計の資本としての贈与」といえるのでしょうか。
「債務の肩代わり」の法的性質
債務の肩代わりは被相続人が相続人に対して無償で行う経済的出捐(支出)といえ、その性質は原則として贈与と同視するのが相当でしょう。
「生計の資本としての贈与」の判断基準
肩代わりした債務の金額の多寡、あるいは被相続人が相続人に対して求償権を放棄(免除)したと認められる事情があるかどうかによって、当該肩代わりが「生計の資本としての贈与」といえるかどうかが判断されるといえます。
具体例
この点、求償権が被相続人によって放棄されたという事情が特に認められない限り、求償権そのものが相続人に承継されるものと考えられ、「生計の資本としての贈与」は存在しないと認定されることになります。
一方、求償権が被相続人によって放棄されたという事情が認められる場合、「生計の資本としての贈与」、すなわち特別受益が認められやすくなります。こうした被相続人による求償権放棄を認めるべき事情としては、被相続人が債務を肩代わりした相続人に対して相当長期間求償権を行使せず放置したことが考えられます。その他にも、被相続人が債務を肩代わりした相続人に対して求償権を行使するどころかむしろその後も積極的な経済的援助を続けた場合などが考えられます。
裁判例
過去の裁判例も「被相続人が、自分が身元保証をしていた共同相続人の夫の勤務先での不祥事について、金銭を支払いそれを同夫に対して求償しなかったことは、当該相続人に対する『相続分の前渡し』として『生計の資本としての贈与』であると解するのが相当」(高松家丸亀審平成3年11月19日)と判示しております。
同審判のポイントは、被相続人による債務の肩代わり自体については、あくまで被相続人自身の保証債務を履行したものであるから特別受益とはみなされないものの、被相続人が共同相続人の元夫に対して求償権を行使せず求償債務を免除したことは、共同相続人に対する「生計の資本としての贈与」にあたり、共同相続人の持戻し義務を肯定したことです。
相続や遺言の問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非お気軽に弊事務所までご相談いただくことをおすすめ致します。